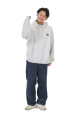素敵な専門家になろう!
旅行・観光、ホテル、ブライダル、旅客サービス(エアライン、鉄道)、テーマパーク、エアポート(空港)、エアカーゴ(航空貨物)などのホスピタリティ産業では、人から「ありがとう!」と言ってもらえる仕事がいっぱい。どれをとっても、しっかりその道を進めば、リストラなんて恐くない「専門職」ばかりです。ちょっとのぞいてみれば、自分のやりたい仕事がきっと見つかるはず。


気になるおしごとを探す
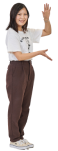


よく見られているおしごと
-
〈旅行・観光〉
メディアセールス
メディアセールスカウンターセールス、アウトセールスに続く第3の...
-

〈ホテル〉
ソムリエ
ソムリエソムリエはワインに関するスペシャリスト。田崎真也さんと...
-

〈ホテル〉
レストランスタッフ
レストランスタッフ料理や飲み物をテーブルまで運び、食後に皿やグ...
-

〈ブライダル〉
ドレススタイリスト
ドレススタイリスト素敵な結婚式には、花嫁の素敵なウェディングド...
-

〈エアライン・航空〉
ロードマスター
ロードマスター分刻みで動く数多くの到着便・出発便に対応するため...
-
〈旅行・観光〉
ツアープランナー
ツアープランナー「旅行会社でやりたい仕事は?」とアンケートをと...
-

〈ホテル〉
セールス(営業)
セールス(営業)どんなに客室や宴会場がデラックスでも、レストラ...
-

〈ホテル〉
プランニング
プランニングホテル業は客室、宴会場、レストランなどの「ハードウ...
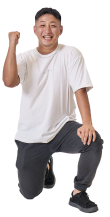


お知らせ